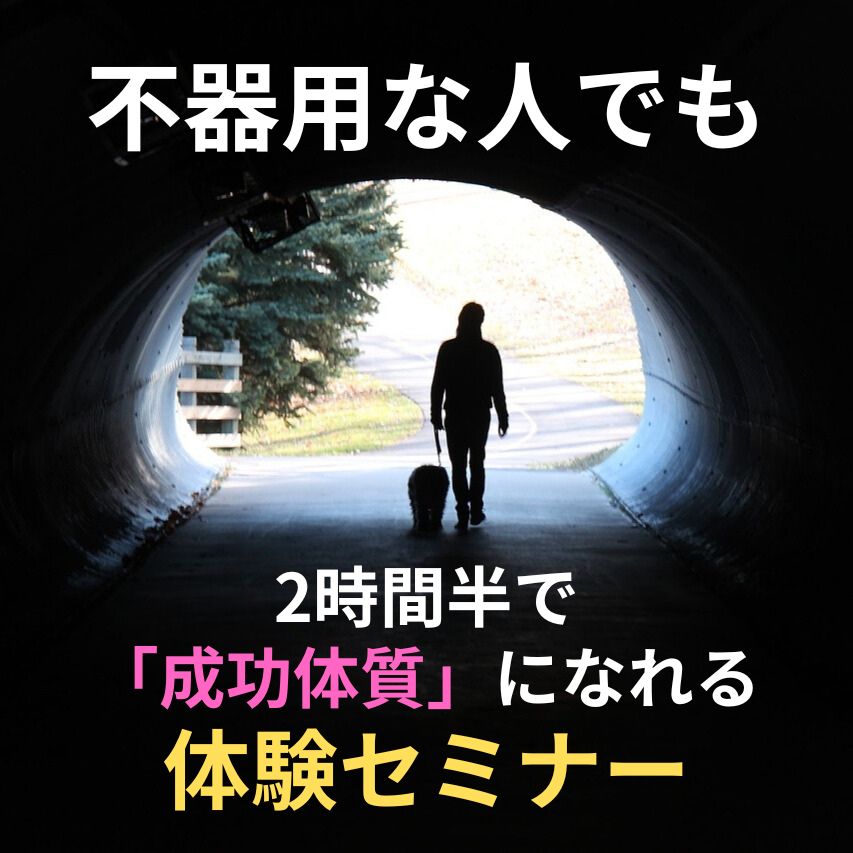いつも私のメルマガをお読みいただき、どうもありがとうございます。往来庵の菊地克仁です。
先日のメルマガで、私のクライアントさんが、お子さんの小学校のことで、「それ、ホントかよ!」という話題を取り上げさせていただきました。別の方から、次のようなお話も伺いました。
正直、「それが現実なのかなぁ・・・」とも感じました。私のサラリーマン時代も思い出しました。今回はそんな話題です。
その小学校の校長先生が、
「我が校は、教師も生徒もオープンマインドで、新しいことにどんどんチャレンジする開かれた教育環境を推進していきます。」
と胸を張って父兄に向かって語ったそうです。先生方も、同じマインドをもった方々がたくさんいたようです。
そこで父兄が集まって、新たな面白いことを学校側に提案しようということになりました。「授業風景や先生の教えていることを、全校生徒の親御さんにも見てもらう環境をつくろう!」ということになったのだそうです。
革新的な先生方が多かったこともあり、原案作りの段階では、現場の先生方からは大きな反対はなかったそうです。
そのアイデアを、父兄たちが校長先生に提案しに行ったときのことです。校長先生の一言から、父兄は校長先生の本音を知ることになりました。校長の言葉は、
「みなさんの言いたいことはよくわかりますが、教育委員会は否定的だと思うので、現実は難しいですね。」
でした。
「新しいことにどんどんチャレンジする開かれた教育環境を創造する」というのは、
「そう告げる校長自身の立場を、父兄の前で自己アピールすることが第一の目的であって、本気で改革を推進する気など、全然ないことがよくわかった。」
ということでした。
「どうやったら、現実化に向けていけるか、是非一緒に考えていきましょう!」などという発言も姿勢も、微塵もなかったそうです。
校長先生に提案しにいった父兄の方々は、「なんだ!それ!」と思ったそうです。「ホンネ」と「タテマエ」がすぐにわかったそうです。
校長の本音は、
「私が教育委員会に睨まれてまで、新たな改革を推進する気なんて、さらさらないですよ!」
ということだったのです。
私も思い起こせば、こういった対応方法は、一般企業などでもよく使われる手法のような気がします。
例えば、「部下からの新たな提案にたして、私はいいと思うよ。でも上がダメだろうなぁ」と言って、それ以上の話題に発展させないようにする中間管理職、あなたの周りにもいませんか?
新たな提案を証拠を残さないように上手に握りつぶして、自分の負担が増えないようにすることには長けた上司です。
「自分が一番大事なの。だから上から睨まれるようなことしたくないの。わかるだろ?君自身の評価も考えた方がいいよ。」
といったところでしょうか?
こんなにあからさまに言う上司はいませんが、部下が真剣であればあるほど、その姿勢はすぐに見抜かれてしまいます。こうした上司の本音の姿勢がわかった時点で、部下からの人望は地に落ちることでしょう。
次から部下は、期待できない上司には何も言わなくなるので、この上司も一安心といったところでしょう。私のサラリーマン時代にもこういう上司はいました。お顔つきやお言葉が昨日のように思い出されます。
組織活動は、共通目的を持つ人の集まるところではありますが、その温度差や考え方はさまざまです。そして、こうしたことをしているうちに、
時間切れになり、結局今まで通り変化しない状態が続く
という例を、私は今までもたくさん見てきました。
特に、ここで取り上げたような小学校などの場合、一番弱い立場の子供たちに、その「しわ寄せ」が行きます。社会の中では、従順で素直な社員などが、その被害を被ることになります。
確かに、あれこれ知恵を使って、組織の中で生き残ることを最重要課題とする生き方もあると思います。ご自身や家族の生活が懸かっているので、当然かもしれません。
が一方で、そっと胸に手を当てて、
「自分は何のためにここにいて、本来は何をする人なんだっけ?」
と、ときどき考えてみることは、誰にとってもきっと無駄ではないと思います。
今回も最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
- 「今までいろいろな心理学を学んだが実践できない!」
- 「潜在意識については知っているけど、使えない!」
- 「もっと自分らしく生きる世界がある筈だが、わからない」
- 「私はこんなもんじゃない筈だ!」
- 「もっと新しい自分に変えていきたい!」
- 「もっと自分を好きになりたい!」
このような方を対象に、オンラインセミナーとオンラインorリアルの個別セッションの2ステップで、潜在能力を引き出す方法をお伝えします。
不器用な人でも2日間で
【成功体質】になれる体験セミナー
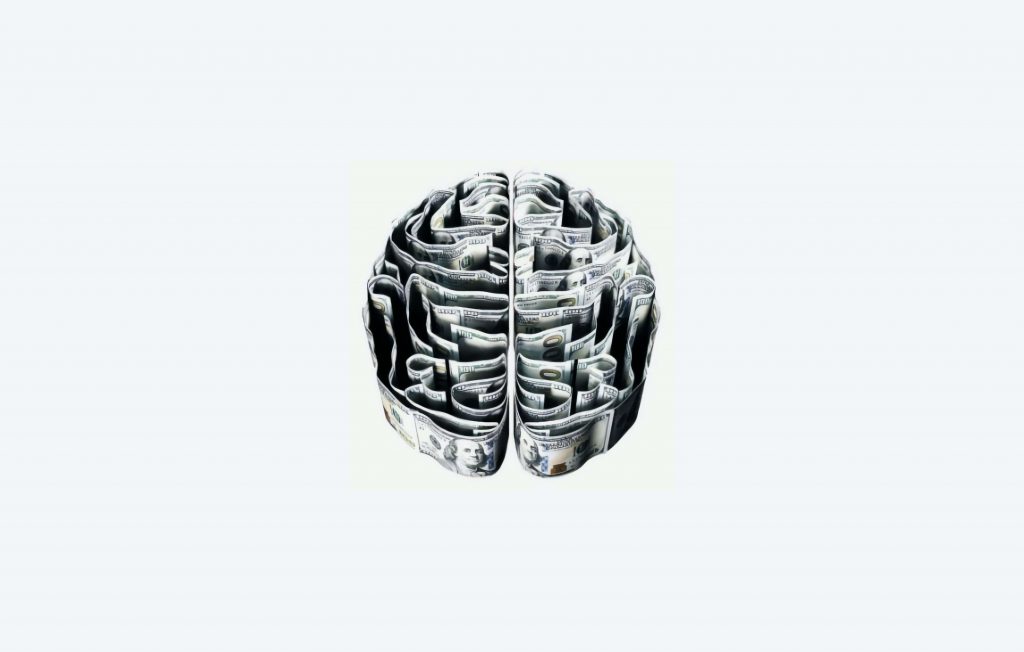
人間であれば誰もが持っている「自分だけの潜在能力」を引き出し、
1. ビジネスと私生活を両立しながら
2. 人間関係に悩むことなく
3. 目標や願望を実現できる
そんな“最高の人生”を送る方法とは?
※別途個人セッションを含むプログラムのため、ご参加いただける人数が限られています。興味がある方は、今すぐ席の確保をお願いいたします。